特別企画
「ヒカルの碁」1巻発売から26周年! 今もなお続く、囲碁ブームを巻き起こした名作
2025年4月30日 00:00
- 【「ヒカルの碁」第1巻】
- 1999年4月30日
2025年4月30日、「ヒカルの碁」の単行本1巻の発売日から26年が経った。(※連載開始は1999年)
「ヒカルの碁」は、原作にほったゆみ氏、作画は「DEATH NOTE」などで有名な小畑健氏という、ふたり体制で連載が始まった。なお、日本棋院所属の女流棋士・梅沢由香里(現:吉原由香里)さんが監修を務めている。
本作が連載されていたのは集英社のマンガ雑誌「週刊少年ジャンプ」。平凡な小学生の少年・進藤ヒカルが天才囲碁棋士・藤原佐為(ふじわらのさい)の霊に取り憑かれたことで囲碁の世界に巻き込まれ、「神の一手」を目指す姿を描く作品となっている。
単行本は全23巻。少年マンガとしては異色の囲碁マンガだったが、小畑氏による繊細な作画と、ほった氏による初心者にもわかりやすいストーリーで人気を博し、囲碁を幅広い世代に浸透させ、囲碁ブームを引き起こした。2000年に第45回小学館漫画賞を受賞、2003年に第7回手塚治虫文化賞新生賞を受賞し、2013年5月時点で累計発行部数は2,500万部を記録している。
2001年10月からは全75話から成るテレビアニメが放映。また、2024年7月5日から14日までサンシャイン劇場にて「歌絵巻『ヒカルの碁』序の一手」も上演されたことが記憶に新しい。
第1部・佐為編
まず初めに「ヒカルの碁」のあらすじについて紹介していく。物語後半の内容についても触れているのでネタバレには注意してほしい。
普通の小学校6年生の進藤ヒカルは、ある日、祖父の家で古い碁盤を見つける。碁盤の血痕に気づいたヒカルは、その碁盤に宿っていた平安時代の天才棋士・藤原佐為の霊に取り憑かれてしまった。
大切な対局において、対局相手のイカサマにより非業の死を遂げた佐為。囲碁のルールも何も知らないヒカルは、「神の一手を極めたい」という佐為にせがまれて、渋々碁を打ち始めることになった。
そんなヒカルの前にある日現われたのが、ヒカルと同じ小学6年生という、塔矢アキラ。アキラが何者かも知らないヒカルは、佐為に言われるままに碁を打って、アキラに勝利するが、アキラはなんとトッププロ棋士・塔矢行洋の息子で、すでにプロ級の腕前を持っている子供だった。
自分の同級生に、自分よりもはるかに高みにいる打ち手がいることにアキラは打ちのめされ、ヒカルを追うようになる。一方、アキラと佐為の囲碁への想いに心を打たれたヒカルは、自分ももっと囲碁を知りたいと思い始め、つたないながらも自分でも囲碁を打ち始めるのだった。
佐為編では、このヒカルとアキラを巡ってのドラマが様々な形で描かれる。アキラが追っているのはヒカルではなく佐為の背中なのだが、ヒカルが自分で碁を打つようになったことで、アキラはやがてヒカルに絶望を感じることとなる。そしてアキラはさっさとプロ棋士として、その道を踏み出してしまうのだった。
今度はヒカルがアキラの背中を追うような形で、ヒカルは囲碁棋士を養成する機関である院生となった。院生として力をつけたヒカルは、やがて佐為に頼らず自分の力でプロ試験に合格する。
ヒカルの公式戦第一局はアキラが相手だったのだが、その対局直前に行洋が過労から心臓発作で倒れ、対局はヒカルの不戦勝となる。行洋の見舞いに訪れたヒカルは、行洋がネット碁をすることを知り、ネットを通してなら、過去最高の打ち手である佐為と現代最高の打ち手である行洋を、戦わせてあげられると気付く。
そのネット碁は佐為の勝利に終わり、勝利に満足する佐為だったが、直後の検討でヒカルは行洋のミスを発見し、佐為が負けていたかもしれないことを口にする。佐為は、ヒカルの指摘に、1000年亡霊として存在してきたのはこの一局をヒカルに見せるためだったのだと悟り、佐為は消えていくのだった。
佐為編の見どころ
佐為編では、ヒカルを取り巻く環境が、次々と変わってゆく。
元々は碁のことを知りもしなかったヒカルが佐為と出会うことで少しずつ碁に興味を持ち始め、アキラと出会い、中学では囲碁部に入り、囲碁部でまた様々なドラマが描かれ、やがて院生となり囲碁部を退部。院生になってからはなかなか上位に上がれないヒカルのジレンマや、プロ試験を受ける人たちの心の揺れ動きなども繊細に描かれている。
子供だらけの囲碁マンガにならないよう、ヒカル(の背後にいる佐為)の才能に目を付けた行洋や緒方などのトッププロたちとの交流も描かれ、佐為の力ではなく自分の力で神の一手に届きたいと思い始めるヒカルの成長には本当に心を打たれたものだ。
ちなみに誰もつっこまないので筆者がここでひとつつっこみたいのは、東京在住という設定のヒカルの家と、その近所にあるらしき祖父の家。その祖父の家に今時蔵があるだなんて、実はヒカルの家って石油王……!?
筆者も最初に「ヒカルの碁」を読んだのはまだ20年以上前で、結婚すらする前の頃だったので、今回この記事執筆にあたって久しぶりに本作を読み直したのだが……東京の地価を知っていれば、こんなくだらないつっこみもしたくなるものだ。
といった冗談はさておき、佐為編で登場する筆者のお気に入りのキャラクターは、院生の伊角。院生1位でプロになる実力を持っていながらメンタルが非常に弱く、いわゆる本番で本領を発揮できず、プロ試験に受かれない、という長年院生止まりの伊角。彼の抱く葛藤などを含め、伊角の生き様は、これまで生きてきた人間の多くが共感できる部分があるのだ。
こういったヒカルを支える脇役たちもいずれも個性的でありながら魅力的で、皆ヒカルとその背後にいる佐為との実力の差に振り回されたりしながらも、やがてヒカル自身の才能を認めていくようになり、そんなヒカルの成長を喜ぶ佐為の姿も見どころのひとつだろう。
第2部・北斗杯編
佐為が消えたことを受け入れられないヒカルはプロ活動を休止し、誰とも囲碁を打たない日々を過ごしていた。そんなヒカルの元に、かつての院生仲間だった伊角が現われて、対局を申し込まれる。その対局のなかで、ヒカルは自分の打った一手が、かつて佐為の打っていた手であることに気付く。佐為から受け継いだ囲碁の中に、佐為が生きているのだ。
ヒカルは再びアキラを見据えて、プロ活動に復帰する。そしてヒカルとアキラの公式初対局を迎え、アキラはヒカルの中に「佐為」がいるのを感じた。佐為の存在をアキラに指摘されたヒカルは、そこに強い喜びを感じるのだった。
プロ棋戦に復帰したヒカルとアキラは、それぞれ若手のプロとして活躍していた。そんな中、18歳以下、日本・中国・韓国対抗で3対3での団体戦「北斗杯」が開かれることとなる。アキラとヒカル、関西棋院所属の社清春の3名が代表選手に選ばれ、ヒカルはなんと大将となった。
結局、北斗杯は日本が3位という結末で終わるのだが、中国チームの団長・楊海はなぜ碁を打つのかもなぜ生きているかも一緒で、遠い過去と遠い未来を繋げるために誰もがいるのだと説き、北斗杯編は幕を閉じるのだった。
北斗杯編の見どころ
全体的には、佐為が消えたあとの後日談に近い話ではあり、ヒカルももちろんアキラと共に成長を続けて、ふたりが打ち解けて非常に良い関係を築けていることが見られる他、ヒカルの周囲の成長もクローズアップされているような内容だ。
北斗杯編では、これまで日本の中でだけ描かれていた囲碁が、実は中国、韓国などもすごく強いのだということが明かされ、世界にはまだまだ強敵がいるのだと知ることとなったヒカル。
なかでも、日本語に不慣れな通訳による誤訳で佐為がかつて憑りついていたという本因坊秀策(江戸時代の囲碁棋士)をバカにされたと感じたヒカルが激昂するシーンは、ヒカルのなかにちゃんと佐為が強い影響を残していることを感じ取れて、とても胸が熱くなった。
しかし結果的には各キャラクターがみんながみんな強くなりすぎて強さのインフレを起こしかけていたため、北斗杯編で幕を閉じている。もっと読みたかったという気持ちもあれど、すっきりと良い幕引きだったのではないかというのが、筆者の感想だ。
美麗な絵と、初心者にもわかりやすい内容で、引き込まれる
本作の一番の魅力は、筆者としては小畑氏による美麗な絵だと思っている。
特に佐為の立ち烏帽子に狩衣を身に纏い、長い髪を下の方で纏めている姿は端麗としか形容するしかなく、非常に雅やかである。もちろん主人公であるヒカルの活き活きとした表情や、一転落ち込んだ姿などの描き分けも素晴らしいのだが、佐為の穏やかさと子供っぽさ、なのに囲碁となるときりりと引き締まり闘志を露わにするあたりは、さすが小畑氏の画力だ。
本作の中心となるのは間違いなくヒカルとアキラというふたりのライバルなのだが、佐為と行洋というライバル同士も、また目が離せない戦いのひとつだったと思う。佐為と行洋がいなければ、間違いなくヒカルの成長もなかっただろう。
そんな佐為が途中で消えてしまうというのは、いなくなった佐為を必死に探し回り、それでも見つからずにヒカルが絶望感を覚えたように、読者である我々もまた、佐為は成仏したのだと知りながらも心を痛めたものだ。
実は「ヒカルの碁」では囲碁の対局における難しいルールについては、ほとんど省かれている。筆者もわかりやすく「ヒカルの碁」のゲーム(コナミデジタルエンタテインメントより発売されたGBA用ソフト「ヒカルの碁」)で囲碁を始めてみたのだが、ルールがどうにもわからず、最初の対戦相手となるあかりちゃんにすら全く勝てないという有様だった。
……というくらい、囲碁はルールを覚えるのが難しいのだ。しかしマンガでは、初心者が読んでいても全く違和感なくないように溶け込める程度の説明がされるだけで、その点が非常に工夫されていた。
素直に、「囲碁がわからなくてもおもしろい囲碁漫画」というのは本作以外ないのではないか(筆者が知らないだけならば申し訳ないのだが)、というくらい、本作は徹底的にルールを知らない読者への配慮がなされており、それでもグイグイと物語に引き込まれたのは、緻密に考えられたほった氏による原作と、それを見事な構図で描きあげた小畑氏の画力によるものだろう。
初心者がわからない用語を用いる時は、あえてアップの構図でビシっと決め、荘厳な雰囲気で読者の心を盛り上げる、といった工夫などもされていた。
ちなみに、初心者でも楽しめる囲碁マンガとあるが、囲碁の盤面については決して手は抜かれていない。盤面の状態は日本棋院所属の女流棋士・梅沢由香里さんの協力でしっかりと考証されているそうだ。残念ながら囲碁を覚えられなかった筆者は、いまだに盤面を見てもさっぱりわからないのだが、囲碁がわかる人が見れば「なるほど」となるような状態になっているらしい。(筆者もそうなりたかった……)
まだまだ続く囲碁ブーム
26年前に原作を読んでいたファンたちが今は子供を持つ世代となり、子供への習い事に囲碁を選択する、というケースも多いようだ。
まだまだ続く囲碁ブーム。囲碁を知らない世代にも向けて簡略化されて描かれていることも多いため、本作で囲碁を覚えていこうとするのは少々難しいが、難解な囲碁への取っ掛かりとなることは間違いない。
ぜひ読んだことがない人も、これを機に少年ジャンプ+などで読んでみてほしい。絵もクセが少なく、老若男女問わず楽しめる作品となっている。なお、東京、大阪、京都で、「ヒカルの碁」原画展の開催が決定しているので、ファンはぜひこちらにも訪れてみてほしい。
┈┈⚪⚫⚪┈┈
— 【公式】ヒカルの碁 │ 原画展 (@hikarunogo_ex)April 25, 2025
空前の囲碁ブームを巻き起こした「ヒカルの碁」
原画展が開催決定!
┈┈⚪⚫⚪┈┈#ヒカ碁展の続報をお楽しみに!
公式サイトhttps://t.co/QXYx74hdTZ#ヒカルの碁pic.twitter.com/9cw0VpRTMc













![週刊少年サンデー 2026年13号(2026年2月25日発売号) [雑誌] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/51BtgWK8guL._SL160_.jpg)

![週刊少年マガジン 2026年13号[2026年2月25日発売] [雑誌] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51Tc2-NPnEL._SL160_.jpg)
![【電子版】月刊コミックビーム 2026年3月号 [雑誌] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/510qLJC5+LL._SL160_.jpg)

![アフタヌーン 2026年4月号 [2026年2月25日発売] [雑誌] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/513xXSf+W5L._SL160_.jpg)
![週刊少年マガジン 2026年12号[2026年2月18日発売] [雑誌] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51igYObv58L._SL160_.jpg)

![ヤングマガジン 2026年13号 [2026年2月24日発売] [雑誌] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51nFWoOD2bL._SL160_.jpg)
![コロコロコミック 2026年3月号(2026年2月14日発売) [雑誌] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51JsckV8IAL._SL160_.jpg)







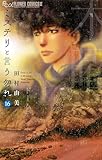






















![SAKAMOTO DAYS 26 (ジャンプコミックス) [ 鈴木 祐斗 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8679/9784088848679_1_3.jpg?_ex=128x128)
![ルリドラゴン 5 (ジャンプコミックス) [ 眞藤 雅興 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7450/9784088847450_1_3.jpg?_ex=128x128)
![チェンソーマン 23 (ジャンプコミックス) [ 藤本 タツキ ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7788/9784088847788_1_9.jpg?_ex=128x128)
![ワンパンマン 35 (ジャンプコミックス) [ ONE ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7221/9784088847221_1_7.jpg?_ex=128x128)
![葬送のフリーレン(8)【電子書籍】[ 山田鐘人 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8522/2000011208522.jpg?_ex=128x128)
![葬送のフリーレン(7)【電子書籍】[ 山田鐘人 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4363/2000010914363.jpg?_ex=128x128)
![葬送のフリーレン(2)【電子書籍】[ 山田鐘人 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6283/2000008946283.jpg?_ex=128x128)
![るろうに剣心ー明治剣客浪漫譚・北海道編ー 10【電子書籍】[ 和月伸宏 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1481/2000019311481.jpg?_ex=128x128)
![黄泉のツガイ(12) (ガンガンコミックス) [ 荒川弘 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3816/9784301003816.gif?_ex=128x128)
![ドラハチ(9)【楽天Kobo限定特典付】【電子書籍】[ 夏川勇人 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4582/2000019644582.jpg?_ex=128x128)
![LV999の村人(20)【電子書籍】[ 岩元 健一 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1021/2000019711021.jpg?_ex=128x128)
![とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の心理掌握(5)【電子書籍】[ 鎌池 和馬 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0521/2000019710521.jpg?_ex=128x128)
![九龍ジェネリックロマンス 12 (ヤングジャンプコミックス) [ 眉月 じゅん ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0649/9784088940649.gif?_ex=128x128)
![とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の心理掌握(5) (角川コミックス・エース) [ 鎌池 和馬 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1172/9784041171172_1_4.jpg?_ex=128x128)
![男女比1:5の世界でも普通に生きられると思った? 〜激重感情な彼女たちが無自覚男子に翻弄されたら〜 3【電子書籍】[ 三藤 孝太郎 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1070/2000019711070.jpg?_ex=128x128)

![チラチラ(6)【電子書籍】[ 小窓際 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1686/2000019711686.jpg?_ex=128x128)
![妖怪学校の先生はじめました!(20) (Gファンタジーコミックス) [ 田中まい ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3441/9784301003441_1_2.jpg?_ex=128x128)
![転生したらスライムだった件(31)【電子書籍】[ 川上泰樹 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5604/2000019605604.jpg?_ex=128x128)
![「壇蜜」(2)【電子書籍】[ 清野とおる ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3338/2000019513338.jpg?_ex=128x128)

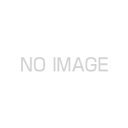
![恋をする日のランジェリー(3) (KC KISS) [ KUJIRA ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8931/9784065428931.gif?_ex=128x128)
![岬くんの不器用な溺愛 8 (マーガレットコミックス) [ 里村 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2366/9784088432366_1_19.jpg?_ex=128x128)
![超深宇宙より愛をこめて(2) (百合姫コミックス) [ アシダカヲズ ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9586/9784758089586_1_3.jpg?_ex=128x128)
![いみちぇん! 1 (あすかコミックスDX) [ 市井 あさ ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2551/9784041172551_1_6.jpg?_ex=128x128)
![八百夜(7)【電子書籍】[ 那州雪絵 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8619/2000019548619.jpg?_ex=128x128)
![アマテラス 2 (花とゆめコミックス) [ 美内すずえ ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5921/59219811.jpg?_ex=128x128)
![アマテラス 1 (花とゆめコミックス) [ 美内すずえ ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5921/59219810.jpg?_ex=128x128)
![[新品]俺の声に堕ちてください (1-2巻 最新刊) 全巻セット 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0065/m4560445440_01.jpg?_ex=128x128)


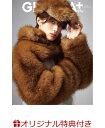

![似鳥沙也加 1st写真集 Ribbon [ 似鳥 沙也加 ] 製品画像:15位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4622/9784048974622_1_6.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定特典】乃木坂46川崎桜 1st写真集『エチュード』(限定絵柄ポストカード1枚) [ 川崎桜 ] 製品画像:14位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1016/2100014821016_1_4.jpg?_ex=128x128)
![斉藤里奈1st写真集 色彩 [ 三瓶 康友 ] 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9175/9784065349175_1_2.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定特典】森香澄ファースト写真集 『すのかすみ。』(限定カバー(ランダム発送で直筆サイン付)) [ 森 香澄 ] 製品画像:12位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7629/2100013837629_1_5.jpg?_ex=128x128)
![STU48 石田千穂 3rd 写真集 (仮) [ 石田 千穂 ] 製品画像:11位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2402/9784087902402_1_10.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定特典】梶田拓希1st写真集 希耀(限定ブロマイド) [ 梶田拓希 ] 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2379/2100014782379_1_3.jpg?_ex=128x128)