特別企画
最強の大罪人たちはいかにしてその罪を負ったのか? 鈴木央氏によるダークファンタジー「七つの大罪」が12周年
2025年2月15日 00:00
- 【「七つの大罪」1巻】
- 2013年2月15日 発売
“これは、いまだ人と、人ならざるものの世界が分かたれてはいなかった古の物語”──漫画家・鈴木央(すずきなかば)氏によるダークファンタジー「七つの大罪」が、単行本第1巻の発売から2025年2月15日をもって12周年を迎えた。同作は2012年より講談社の「週刊少年マガジン」にて連載をスタート、以降2020年まで展開を続けた長編作品で、今もその直系の続編となるマンガ「黙示録の四騎士」が、同じく「週刊少年マガジン」連載されている。
作品タイトルにもなっている七つの大罪といえば、マンガ好きにとってはおなじみのワード。憤怒、嫉妬、強欲、怠惰、色欲、暴食、傲慢──単語としての表現や表記される序列・順番などは年代や媒体によって多少の差異があるが、概要としてはキリスト教世界における罪源(罪を犯す動機になる感情や欲望)としてタブー視されてきたものを指す。マンガに限らず、創作の世界において広く取り扱われてきたテーマで、有名な例としては「鋼の錬金術師(スクウェア・エニックス)」に登場するホムンクルスのネーミングなどが挙げられる。
ここからはストーリーに触れつつ、本作において“七つの大罪”という言葉がどのように用いられているのか、さらに作中で様々な種族が登場する理由についても紹介したい。なお、記事後半には「七つの大罪」物語終盤に関する内容があるためネタバレには注意して欲しい。
大罪人の烙印を押された、義に厚く気も良い騎士たち。その真相を求める好奇心でページを捲る手が止まらない!
本作の舞台は、騎士文化が根付く中世ヨーロッパ的な世界観の大地・ブリタニア。なかでも、隆盛を極めるリオネス王国が物語の中心となっている。その第3王女であるエリザベスは、本来国王に仕えるべき聖騎士たちが起こしたクーデターにより、国民が苦しめられている現状を憂いて出奔。大罪人の集まりと言い伝えられながら、同時に最強の騎士団でもあったと噂される“七つの大罪”に助けを求めるため放浪していたところ、主人公・メリオダスが営む酒場にたどり着く。実はそのメリオダスこそが“七つの大罪”団長であり、とある事情から彼も団員を集めるつもりだったという。こうして、メリオダスとエリザベスの“七つの大罪”団員探しの旅が始まるのだった。
本作において、タイトルにもなっている“七つの大罪”は前述した“伝説の騎士団の名”として登場する。この騎士団は、憤怒や嫉妬など、七つの大罪に数えられる罪源に関連した罪を犯したとされる、大罪人7名によって組織されていた。しかし、その団員たちは誰もが義に厚く、気も良い人物ときている。最強の大罪人たちは、過去にどのような罪を犯したのか? 物語序盤では、それぞれに押された烙印とキャラクター設定のギャップから生まれる好奇心が推進力となって、グングン作品に惹き込まれていく。ここで、そんな騎士団“七つの大罪”を中心としたキャラクターたちを紹介しておきたい。
・ メリオダス
主人公、「憤怒の罪(ドラゴン・シン」のメリオダス。巨大な豚の頭の上に建てられた酒場「豚の帽子亭」の店主であり、騎士団“七つの大罪”の団長。見た目は年端もいかない少年のようでありながら、基本的には何事にも動じない器の大きさを感じさせる振る舞いを見せる。とある事情から肌見放さず背負っている剣は刀身が折れているが、戦闘時は相手の魔力を倍以上に跳ね返す技「全反撃(フルカウンター)」を駆使する。リオネス王国第3王女・エリザベスが助けを求めに豚の帽子亭へと転がり込んできたところから、本作の物語が動き出す。
・ エリザベス・リオネス
長い銀髪とその前髪で右目を隠したルックスが印象的な、リオネス王国第3王女。王国の騎士たちがクーデターを起こし、戦の準備のため民を苦しめる様を見て、助けを求めて彷徨っていた。大罪人とされるも、かつては王国最強の名をほしいままにした伝説の騎士団“七つの大罪”こそが現状を打破し得ると考えていた。メリオダスと出会い、その正体を知ってからは「豚の帽子亭」ウェイトレスとして行動をともにし、“七つの大罪”を探す旅に出る。
・ ホーク
「豚の帽子亭」のマスコット的存在になっている、世にも珍妙なしゃべる豚。メリオダスは酒場の店主でありながら壊滅的に料理が下手であり、その料理を口にした客が嘔吐することから、その吐瀉物や残飯を食べて後片付けをする「残飯処理騎士団」団長を名乗っている。豚の帽子亭が括り付けられている巨大な豚を「おっかあ」と呼んでいる。
・ ディアンヌ
作中で2番目に登場した“七つの大罪”団員、「嫉妬の罪(サーペント・シン」のディアンヌ。人間とは異なる種族・巨人族の少女で、生来戦いを好まない優しい性格。鉄を飴のようにねじ曲げたり、地層を槍のように隆起させたりと大地に関連する魔力「創造(クリエイション)」を持つ。
・ バン
「強欲の罪(フォックス・シン」のバン。れっきとした人間だが、彼が罪人となった出来事をきっかけに不老不死の肉体となっており、「不死身の(アンデッド)バン」の異名も持つ。治安の悪い町に生まれ育ち、“七つの大罪”団員となるまでは盗賊をしていた。団長であるメリオダスとは無二の親友であり、顔を合わせると周囲の地形が変形するほど戦う(というよりはじゃれ合っている)のが2人にとっての慣例となっている。
・ キング
「怠惰の罪(グリズリー・シン)」のキング。妖精族であり、本名はハーレクイン。妖精たちが暮らす妖精界、そこに鎮座する神樹によって選ばれた、3代目の妖精王でもある。見た目を自由に変えることができ、“七つの大罪”が王国にて活躍していた頃は恰幅の良い壮年の男性の姿をしていたが、本来は少年のような姿をしている。神樹から作られ、様々な形態に変化できる神器・霊槍シャスティフォルを操るほか、ちょっとした切り傷を致命傷にしたり、少量の毒による状態悪化を深刻なものにしたりと、悪性ステータスを進行させる魔力「災厄(ディザスター)」を駆使する。
・ ゴウセル
「色欲の罪(ゴート・シン)」のゴウセル。メガネをかけた中性的な男性のような姿をしているが、その正体はとある魔術師によって作られた人形。作中では、無機質で特徴的な喋り方をするとされている。他人の記憶や認識を読み取り、操ることができる魔力「侵入(インベイション)」を持つ。人形である自分にはない“心”を欲しがっており、それを行動原理として他者の記憶を改変したり封じてしまうことがあり、それがトラブルを引き起こすことも。
・ マーリン
「暴食の罪(ボア・シン)」のマーリン。魔術に精通したミステリアスな美女で、新興国キャメロットの王であるアーサー=ペンドラゴンの友であり、側近的な役割を務める。かの「アーサー王物語」におけるキングメーカー・マーリンの立ち位置にいる人物であり、彼女の存在によって「七つの大罪」という作品は、鈴木央氏が構想する「アーサー王物語」の前日譚であることがうかがえる。自身が発動した魔法を永久的に持続させる魔力「無限(インフィニティ)」を持つ。
・ エスカノール
「傲慢の罪(ライオン・シン)」のエスカノール。普段は小柄で気弱な男性だが、彼に備わる魔力「太陽(サンシャイン)」の効果によって、正午に近づくにつれて強大に、傲慢になる“七つの大罪”最強の騎士。灼熱の太陽をその身に顕現させるがごとき魔力で、あらゆるものを焼き尽くす。“七つの大罪”が解散となってからは、誰の目にも留まらないような穴蔵に「麗しき暴食亭」という酒場を開業し、生計を立てていた。
様々な種族による誤解や偏見が生む混乱とドラマ、それを乗り越えた先にあるカタルシスがミソ
記事冒頭やキャラクター紹介でも少し触れたように、本作には人間以外にも巨人族や妖精族といった、様々な種族が登場する。また、そのほか魔神族と女神族という種族も存在し、人狼(ウェアウルフ)や狐男(ウェアフォックス)などもスポット的に登場する。
「七つの大罪」の作品世界では、本編開始からさらに3000年前となる古の時代、魔神族と、女神族を主としたその他種族が対立した聖戦が起きており、その聖戦は未来予知の魔力を持つリオネス国王によって再来することが予言されている。協力関係にはあるものの、種族が異なるが故に本心では理解し合えないという価値観が根底に透けて見えるキャラクターたち、また相互理解の足りなさから生まれる偏見や対立、それらとは反対に、種族を超えた美しい純愛……本作において、特にこの“多種族性”は重要な意味を持つ。
多種族が同居していることにより、様々な問題を抱えていることが示唆される世界において、七つの大罪の団員たちの関係性はその縮図にもなっている。今はまだ話せない秘密、それが生む疑心暗鬼、団員たちが引き起こした、あるいは遭遇した悲劇的な出来事の裏では何が起きていたのか……そもそもが、誤解や策略によって濡れ衣を着せられた“七つの大罪”という騎士団が主役となる作品だ。その混乱が生むドラマや、それを乗り越えた先にあるカタルシスが「七つの大罪」という作品のミソだろう。
ちなみに、物語の舞台の名がブリタニアであることに加えて、マーリンやアーサーという名前のキャラクターが登場することにより、本作が「アーサー王物語」の前譚であることがわかる構造になっている。
鈴木央氏が描く「アーサー王物語」の前日譚が整い、ついに円卓の騎士たちが動き出す
ここからは関連作品を含む余談となるが、筆者が初めて鈴木央氏の作品に触れたのは、「週刊少年ジャンプ(集英社)」にて1998年から2002年まで連載されていたマンガ「ライジングインパクト」。ゴルフをテーマにしたスポーツマンガで、当時の筆者は小学生だったこともあり、ゴルフというものがよく理解できずたまに読むくらいの関係性であった。一方で作品中に、ガウェインやランスロットなど、「アーサー王物語」に登場する著名な騎士から取られたキャラクターたちの名前がずっと記憶に残っていた(下手をすると筆者が円卓の騎士たちの名前に初めて触れた作品かもしれない)。
一方、本記事で取り扱っている「七つの大罪」はTVアニメから入り、その面白さから原作を読み始めたクチだ。それまで自分の中では前述の経緯から鈴木央氏=円卓の騎士の名を自作キャラクター名に引用している漫画家、という印象が強かったものの、「七つの大罪」にも触れて「アーサー王物語」の存在が、鈴木央氏の作家性に色濃く影響を与えていることに時を超えて気付けたことはなかなか得がたい体験だった。
「七つの大罪」の最終盤では、メリオダスの子どもがトリスタン、バンの子どもがランスロットであることが判明する。鈴木央氏が描く「アーサー王物語」の前日譚が整い、ついに円卓の騎士たちが動き出すことを予感させる幕引きだ。そんなトリスタンとランスロットが主要キャラクターとして登場するマンガ「黙示録の四騎士」は、すでにコミックス第19巻まで刊行されているほか、TVアニメも2期まで制作されている。「七つの大罪」からも引き続き多くのキャラクターが登場しているので、ぜひこちらも確認してほしい。
(C)鈴木央・講談社


















![週刊少年サンデー 2026年13号(2026年2月25日発売号) [雑誌] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/51BtgWK8guL._SL160_.jpg)


![週刊少年マガジン 2026年13号[2026年2月25日発売] [雑誌] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/51Tc2-NPnEL._SL160_.jpg)
![週刊少年チャンピオン2026年13号 [雑誌] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51PyY5L7bbL._SL160_.jpg)
![【電子版】月刊コミックビーム 2026年3月号 [雑誌] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/510qLJC5+LL._SL160_.jpg)
![アフタヌーン 2026年4月号 [2026年2月25日発売] [雑誌] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/513xXSf+W5L._SL160_.jpg)


![週刊少年マガジン 2026年12号[2026年2月18日発売] [雑誌] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51igYObv58L._SL160_.jpg)





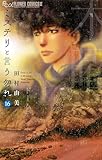
























![真夜中ハートチューン(9)【電子書籍】[ 五十嵐正邦 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2661/2000017892661.jpg?_ex=128x128)
![真夜中ハートチューン(8)【電子書籍】[ 五十嵐正邦 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8309/2000017128309.jpg?_ex=128x128)
![くろアゲハ〜カメレオン外伝〜(14)【電子書籍】[ 加瀬あつし ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6167/2000007716167.jpg?_ex=128x128)
![ブラックチャンネル(14) (コロコロコミックス) [ きさいち さとし ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2571/9784091542571.gif?_ex=128x128)
![葬送のフリーレン(15) (少年サンデーコミックス) [ 山田 鐘人 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3465/9784098543465_1_2.jpg?_ex=128x128)
![名探偵コナン(104) (少年サンデーコミックス) [ 青山 剛昌 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8509/9784098528509_1_13.jpg?_ex=128x128)
![ワンパンマン 36 (ジャンプコミックス) [ ONE ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8914/9784088848914_1_4.jpg?_ex=128x128)
![SPY×FAMILY 16 (ジャンプコミックス) [ 遠藤 達哉 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5272/9784088845272_1_7.jpg?_ex=128x128)
![SPY×FAMILY 15 (ジャンプコミックス) [ 遠藤 達哉 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3377/9784088843377_1_9.jpg?_ex=128x128)
![SPY×FAMILY 14 (ジャンプコミックス) [ 遠藤 達哉 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1540/9784088841540_1_3.jpg?_ex=128x128)
![宇宙兄弟(17)【電子書籍】[ 小山宙哉 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0367/2000000230367.jpg?_ex=128x128)
![宇宙兄弟(22)【電子書籍】[ 小山宙哉 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2691/2000000192691.jpg?_ex=128x128)
![宇宙兄弟(14)【電子書籍】[ 小山宙哉 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4155/2000000184155.jpg?_ex=128x128)
![宇宙兄弟(21)【電子書籍】[ 小山宙哉 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9588/2000000159588.jpg?_ex=128x128)
![宇宙兄弟(18)【電子書籍】[ 小山宙哉 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5448/2000000155448.jpg?_ex=128x128)
![宇宙兄弟(19)【電子書籍】[ 小山宙哉 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0741/2000000160741.jpg?_ex=128x128)
![宇宙兄弟(16)【電子書籍】[ 小山宙哉 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4614/2000000124614.jpg?_ex=128x128)
![宇宙兄弟(13)【電子書籍】[ 小山宙哉 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4052/2000000104052.jpg?_ex=128x128)
![宇宙兄弟(20)【電子書籍】[ 小山宙哉 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9891/2000000099891.jpg?_ex=128x128)
![宇宙兄弟(15)【電子書籍】[ 小山宙哉 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4402/2000000004402.jpg?_ex=128x128)

![ひるなかの流星 12【電子書籍】[ やまもり三香 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1148/2000002921148.jpg?_ex=128x128)
![ひるなかの流星 11【電子書籍】[ やまもり三香 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3581/2000002673581.jpg?_ex=128x128)
![ひるなかの流星 10【電子書籍】[ やまもり三香 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2728/2000002322728.jpg?_ex=128x128)
![ひるなかの流星 9【電子書籍】[ やまもり三香 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4075/2000002144075.jpg?_ex=128x128)
![ひるなかの流星 8【電子書籍】[ やまもり三香 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/7431/2000001877431.jpg?_ex=128x128)
![ひるなかの流星 7【電子書籍】[ やまもり三香 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6224/2000001606224.jpg?_ex=128x128)
![ひるなかの流星 6【電子書籍】[ やまもり三香 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4333/2000000054333.jpg?_ex=128x128)
![【電子版】花とゆめ 2号(2026年)【電子書籍】[ 花とゆめ編集部 ] 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4726/2000019404726.jpg?_ex=128x128)
![【電子版】花とゆめ 1号(2026年)【電子書籍】[ 花とゆめ編集部 ] 製品画像:19位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3395/2000019303395.jpg?_ex=128x128)
![豊島心桜 1st写真集 『心桜ばかり』 [ 豊島 心桜 ] 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1870/9784087901870_1_42.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定特典】辰巳ゆうとセカンド写真集(仮)(初回限定生写真1枚(Aタイプ)) [ 辰巳ゆうと ] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9158/2100014839158_1_2.jpg?_ex=128x128)
![宇佐美なお 1st写真集 『 U 』 [ 西條 彰仁 ] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6625/9784847086625_1_4.jpg?_ex=128x128)
![江頭2:50還暦記念写真集 正面突破 [ 二階堂 ふみ ] 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5150/9784096825150_1_2.jpg?_ex=128x128)