特別企画
ゼブラが紙でも仮想空間でも自在に書/描ける「kaku lab.(カクラボ)」を発表!AIをフル活用した新たなクリエイティブ体験
2025年2月20日 16:04
- 【kaku lab.】
- 2月20日 発表
ゼブラは2月20日、リアルタイム3Dvisual生成プラットフォーム「kaku lab.(カクラボ)」の発表会をゼブラ本社にて開催した。今回は技術発表の側面が強く、現状今後の展開、発売予定については未定となっている。
「kaku lab.」は既存の筆記具の技術にXR(クロスリアリティ)と生成AIを組み合わせることで新しい手書き体験ができる技術。センサーを内蔵し通常の筆記具の機能も備えた「T-Pen」、ペンの動きを仮想空間で再現できる「kaku XR」、複数の生成AIを組み合わせた「kaku AI」の3つを合わせることで、仮想空間上で書いたものを平面化したり、3Dモデルに起こしたりすることができるほか、同じ仮想空間を共有して共同作業をする用途なども想定されている。
なお、「kaku lab.」全体の企画開発はゼブラ、「T-pen」のセンサーが搭載された基盤設計と実装をNTマイクロシステムズ、AIのシステムをインタラクティブラボラトリーが担当する共同プロダクトとなる。
発表会では同社代表取締役社長の石川太郎氏、取締役執行役員の畦地 教子氏、新規研究開発室 室長の岩間卓吾氏が登壇。「kaku lab.(カクラボ)」のポイントや開発背景などが語られたほか、実際に「kaku lab.」を用いたデモンストレーションも行なわれた。
空間に絵を描いてAIで清書&立体化!「kaku lab.」デモでは可能性の一端を垣間見た
発表会では実際に「kaku lab.」を用いて、岩間氏によるデモンストレーションが行なわれた。内容としてはヘッドマウントディスプレイ(ここではMeta Quest 3が使用された)を装着し、「T-Pen」を用いて空間に絵を描き、それを「kaku XR」内のキャンバスに平面のイラストとして転記。さらにそのイラストを「kaku AI」によって清書、3Dモデル化するというものだった。
「kaku lab.」は先述の通り、「T-Pen」と「kaku XR」、「kaku AI」の組み合わせにより、現実の紙にでも仮想空間にでも書く、あるいは描くことのできるプラットフォームだ。「T-Pen」は本体にセンサーを搭載しており、書いているときの速度や角度、筆圧、時間などのデータを取得。これらのデータを蓄積、別のデバイスへの転送も可能な仕組みになっているほか、もちろん紙に書くため通常の筆記具の機能も備えている。
「kaku XR」はヘッドマウントディスプレイをはじめ、PCやタブレットなど様々なデバイスで表示できる仮想空間。「T-Pen」に内蔵されたセンサーとの連動により、、仮想空間内で空中を含め位置を問わず自由に書くことができる。一方の「kaku AI」はGPT-4oやStable Diffusion XL、Tripo AIなど、複数のAIを跨いで必要なAPIを必要なときに呼び出せる仕組みを備えている。これらの組み合わせによって、仮想空間で空中に絵を描き、キャンバスに転記し、描いた絵を清書し、3Dモデルに起こすことが可能となっているわけだ。
本日お披露目された「kaku lab.」はまさに技術発表という段階にあり、今後のビジネスモデルや販売方法、法人向けか個人向けかというところも含めて検討中だという。現段階でも「T-Pen」のセンサーを「kaku lab.」以外の用途で活かすことや、複数のAIを組み合わせて使える仕組みと拡張性の高い設計を備えた「kaku AI」をクリエイティブ用途に限らず、医療や教育、エンタテイメントなど多様な分野で活用していくことなどを想定しており、現在共に「kaku lab.」で新たなチャレンジに漕ぎ出してくれるビジネスパートナーを募集している。
「ハイマッキー」などで知られる老舗文房具メーカーのゼブラが、そのノウハウを活かしながらAIやXRを用いた最新技術に取り組む「kaku lab.」。デモではイラストの立体化に留まったが、発表会で言及があったように仮想空間での複数人による同時作業、生成AIのクリエイティブ向け用途をフルに活かした構造は他のジャンル、例えばフィギュアの造形やゲーム制作などにも有用に感じる。今後のブラッシュアップ、あるいはビジネスパートナー次第では、当初の構想を大きく超える可能性を秘めていると感じた。今後の展開も注視していきたい。

























![週刊少年サンデー 2026年10号(2026年2月4日発売号) [雑誌] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/51g8hG9uilL._SL160_.jpg)
![週刊少年マガジン 2026年10号[2026年2月4日発売] [雑誌] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51u-XP4mZML._SL160_.jpg)



![週刊少年マガジン 2026年9号[2026年1月28日発売] [雑誌] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/51jJtG5kxfL._SL160_.jpg)
![週刊少年チャンピオン2026年10号 [雑誌] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51kN6piaCyL._SL160_.jpg)
![ヤングマガジン 2026年10号 [2026年2月2日発売] [雑誌] 製品画像:8位](https://m.media-amazon.com/images/I/51p-AWjGNfL._SL160_.jpg)
![【電子版】ガンダムエース 2026年3月号 No.283 [雑誌] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZgjR21BiL._SL160_.jpg)






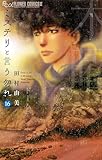


























![化物語(4)【電子書籍】[ 西尾維新 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2612/2000006912612.jpg?_ex=128x128)
![ゴーストフィクサーズ 7 (ジャンプコミックス) [ 田中 靖規 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8921/9784088848921.gif?_ex=128x128)
![2.5次元の誘惑 セミカラー版 25【電子書籍】[ 橋本悠 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1294/2000019511294.jpg?_ex=128x128)
![今朝も揺られてます 4 (少年チャンピオン・コミックス) [ 増田英二 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2768/9784253012768.gif?_ex=128x128)
![一旦カフェにしませんか? 上 (ジャンプコミックス) [ mato ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8648/9784088848648_1_9.jpg?_ex=128x128)
![ドラゴンクエスト4コママンガ劇場 ニセ勇者本 (ガンガンコミックス) [ 柴田亜美 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0792/9784301000792_1_13.jpg?_ex=128x128)
![彼女がクズを愛するワケは。(3) (ガンガンコミックスpixiv) [ 池田ルイ ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2895/9784301002895_1_2.jpg?_ex=128x128)
![OUT 29 (ヤングチャンピオン・コミックス) [ 井口達也 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3079/9784253013079.gif?_ex=128x128)
![名探偵コナンの暗号博士 まんがで学べる!コナン博士シリーズ (ビッグ・コロタン) [ 青山 剛昌 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2353/9784092592353_1_41.jpg?_ex=128x128)
![ミナミの帝王 (188) 完 (ニチブンコミックス) [ 天王寺 大 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3741/9784537173741.gif?_ex=128x128)
![白竜HADOU (48) (ニチブンコミックス) [ 天王寺 大 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3765/9784537173765.gif?_ex=128x128)
![地政学ボーイズ ~国がサラリーマンになって働く会社~ 8 (ヤングチャンピオン・コミックス) [ 理央 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0207/9784253010207_1_27.jpg?_ex=128x128)
![名探偵コナンの防犯博士 まんがで学べる!コナン博士シリーズ (ビッグ・コロタン) [ 青山 剛昌 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2391/9784092592391_1_47.jpg?_ex=128x128)



![アンゴルモア 元寇合戦記 博多編 (2)【電子書籍】[ たかぎ 七彦 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0046/2000008270046.jpg?_ex=128x128)
![うるわしの宵の月(3)【電子書籍】[ やまもり三香 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5521/2000010535521.jpg?_ex=128x128)
![こんなの、しらない(22) (フラワーCアルファ) [ 梨月詩 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3613/9784098733613.gif?_ex=128x128)
![花よりも花の如く 24 (花とゆめコミックス) [ 成田 美名子 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2620/9784592222620_1_30.jpg?_ex=128x128)
![神さま学校の落ちこぼれ 13 (花とゆめコミックス) [ 赤瓦 もどむ ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5683/9784592225683_1_13.jpg?_ex=128x128)
![3月の霹靂 2 (花とゆめコミックス) [ 池 ジュン子 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2286/9784592222286_1_23.jpg?_ex=128x128)
![ぼくは地球と歌う 「ぼく地球」次世代編II 10 (花とゆめコミックス) [ 日渡 早紀 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2934/9784592222934_1_18.jpg?_ex=128x128)
![なのに、千輝くんが甘すぎる。(13) (KC デザート) [ 亜南 くじら ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1636/9784065411636_1_37.jpg?_ex=128x128)
![初めて恋をした日に読む話 19 (マーガレットコミックス) [ 持田 あき ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1666/9784088431666_1_18.jpg?_ex=128x128)
![初めて恋をした日に読む話 18 (マーガレットコミックス) [ 持田 あき ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0980/9784088430980_1_18.jpg?_ex=128x128)
![沼すぎてもはや恋(5) (KC デザート) [ 空垣 れいだ ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8757/9784065358757_1_50.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】乃木坂46 梅澤美波2nd写真集 透明な覚悟(限定カバー) [ 東 京祐 ] 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0479/2100014730479_1_3.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】超ときめき宣伝部 吉川ひより1st写真集(フォトカードA(トレカサイズ)1枚) [ 吉川 ひより ] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4415/2100014804415_1_2.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定デジタル特典】QuizKnock10周年スペシャルブック 十字路(ロケ撮影メイキング映像 ダウンロード) [ QuizKnock ] 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9436/9784048979436_1_9.jpg?_ex=128x128)