レビュー
「栄光なき天才たち」レビュー
歴史に埋もれた人々の悲劇を見事に描く"偉人伝"
2024年12月2日 00:00
- 【栄光なき天才たち】
- 週刊ヤングジャンプにて1986年から1992年まで連載
今年、2024年は第33回オリンピックが開催された年である。様々な競技が行われる中で、一部の国のメダルを取れなかった選手の話を聞く度に、脳裏に浮かんでくる漫画の存在がある。それは森田信吾氏(一部の原作は伊藤智義氏)によって描かれた「栄光なき天才たち」だ。
「栄光なき天才たち」(全17巻)は1986年から1992年まで「週刊ヤングジャンプ」で連載されていた作品だ。以降も1993年から1994年には「新・栄光なき天才たち」(全3巻)、「栄光なき天才たち2009」(原案・新山藍朗氏)、「栄光なき天才たち2010」、「栄光なき天才たち2011」(監修・鈴木一義氏/原案・矢吹明紀氏)と3年連続で続編が掲載されていた。
語り継がれるべき偉業を為しながらも、不遇な人生を送ることとなった様々な人物の物語を描いたこの作品は、上記のように何度も続編が出たことから多くの人々の心を動かしたことがわかる。実際、私も心に抜けない楔を打ちつけられた。きっと生涯、オリンピックが開催される度にこの作品を思い出すのだろう。
そんな影響を与えた作品「栄光なき天才たち」をぜひ紹介したい。
悲運の物語だからこそ心を激しく揺さぶられる
「栄光なき天才たち」は偉業を為した人物たちの人生をオムニバス形式で描いた、いわゆる伝記であるが、一般的な伝記ではない。取り上げている人物が、例えば電話の発明者とされるグラハム・ベルではなく、ベルに2時間の遅れをとり発明者になれなかったエリシャ・グレイであるというように、偉業を為しながらも認められず歴史に埋もれてしまった人物、素晴らしい発見・発明をしていながら生きているうちは全く認められないまま亡くなってしまった人物、認められ名声を得て華々しい生活を送りながらも辛い環境にいたり転落してしまった人物と、不遇な人物たちだからだ。
成功者である人物の伝記は数多い。それらを読むと、「すごいなぁ」という尊敬の念や「見習わなくては」という襟を正すような正の意識を持つ。しかし「栄光なき天才たち」で偉大な功績を残しながらも報われなかった人達の話を知ると、悲運な状況に対する怒りや悲しみ、苦しさといった負の感情が押し寄せてくる。通常の伝記に比べ、「栄光なき天才たち」のドラマは感情の振れ幅は圧倒的に大きく、読者の印象に残る。それがこの作品が多くの支持を集めた理由だろう。
私自身、このマンガを通じて、正当な評価を与えられず若くして亡くなってしまうノルウェーの数学者ニールス・アーベルの扱いに「なぜ!」と悔しさと憤りを感じ、小説家・樋口一葉と女優・マリリン・モンローという正反対な2人の女性の人生に似たような遣り切れなさを味わった記憶は今でも忘れていない。
また、「栄光なき天才たち」の特徴のひとつとして、実に多彩な分野の人たちを取り上げている点がある。科学者・医者・数学者等の学問系が多いが、スポーツ選手も陸上・水泳・野球・ボクシングと様々だ。他にも小説家や映画監督や女優・歌手等の芸能に携わる人々、そして経済界やジャーナリスト。あまり一般に知られていない人から、世界中が知っている大スターまで、知名度も様々だ。また、個人だけではなく、理化学研究所・鈴木商店・東大野球部・満鉄超特急あじあといった団体を取り上げている。
それだけ多くの分野、そして同じ分野でもひとりひとり違う悲劇が存在している。それだけ多くの人生が描かれていれば、その幾つかは琴線に触れるものがあるのではないだろうか。
自分の一部になった物語
現に、強烈に私の心を捕らえ忘れられなくなっている物語がある。それは5巻を丸々1冊使って描かれた、東京オリンピックに出場した長距離走・マラソン選手の「円谷幸吉」と「アベベ・ビキラ」である。円谷幸吉は東京オリンピックで銅メダルの結果を残しながらも、その後の大きな期待の中で不幸が重なった結果、自死してしまった人物だ。
筆者は1964年の2人が出場した東京オリンピックの頃は生まれてはいなかったが、昭和を生きてきた者として円谷の名前は知っていた。しかし彼について聞こえてくる内容は「国にあれだけ支援され期待されていたのに良い結果を残せなかった」というあまり良いものではなく、子供心にそんな風に言われて可哀想にと思っていた。
しかしこの作品で彼の人生を垣間見ることになりそんな感情は吹き飛んだ。円谷が東京オリンピック以降、腰の持病の悪化、好きな女性との破談と師との別れ、徐々に追い詰められていく様子が描かれていた。特に、家族の写真を大事にし、「どんな辛いことも妻と子供たちがいれば乗りこえられる」と円谷に語ったアベベと、次のメキシコでのオリンピックの前という大事な時期に結婚などとあり得ないと自衛隊幹部候補生学校に反対され、心の支えとなるだろう家族を持てなかった円谷の対比の演出は見事で、より一層円谷の辛さが際立っていた。
円谷の絶望し自死するまでに至る姿を遺書に書かれたていた文言と共に丁寧に描かれており、そのあまりの痛ましさに単に可哀想というだけではなく我がことのように胸が苦しくなった。
それでも次々と出る続巻に、円谷の話も多数の悲劇の中の1つとなり思い出さなくなった頃、1992年のアルベールビルオリンピックが行われた。そのオリンピックの中で、子供の頃から応援していたフィギュアスケートの伊藤みどり選手が銀メダルを取った際、「ごめんなさい」という言葉が出てきたのを見てあまりの悲しさと憤りに震えた。
団体競技で致命的なミスをしたならともかく、個人競技でそんな言葉は聞きたくなかった。競技を見て、私は応援していたし、前日6位からの逆転劇に感動していたし、なにより、トリプルアクセルを成功させて「よかったね」と心から嬉しく思っていた。もし思う通りの成績を残せなかったというなら、自分の為に悲しんだり悔しがったりして欲しかった。けれど伊藤選手にまず真っ先に訪れたのは、国の為に金メダルをとることが出来なかった申し訳なさなのかと思うと辛くて堪らなかった。と同時に、「栄光なき天才たち」の円谷のストーリーが私自身の中に鮮明に蘇った。
アルベールオリンピックの2か月後、「これ以上頑張れない」と伊藤選手が引退した時もまた、自死した円谷の場面が思い起こされた。国の為に頑張り、国の期待に応えられずに追い詰められていく選手たち。「栄光なき天才たち」の中には、円谷以外にも「勝たずして帰ってくるな」という言葉と共にオリンピックに臨み、成果を上げられなかった人物もいる。彼らの存在は、オリンピックの影として4年毎に私の中で追想される。
伊藤選手はその後、プロに転向しアイスショーに出たり世界フィギュアスケート殿堂入りをしたり、フィギュアスケートの解説者として活動したり、近年では国際アダルト選手権に出場したりと活躍してファンのひとりとして嬉しい限りであるが、1992年の彼女の言葉は自分の中に、「栄光なき天才たち」という作品が根付いてしまっていることを自覚させたのだ。
作品を支える作者たちの力
この作品は一貫して森田信吾氏が作画を行っているが、第一部の「栄光なき天才たち」の1、4、6、8、14巻には原作として伊藤智義氏が参加している。伊藤智義氏は漫画の原作者としても活躍しているが、同時に計算機科学者、千葉大学 工学部長・大学院工学研究院長でもあり、平成24年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞(研究部門)をはじめ数々の受賞をしている。
著書にも「GPUプログラミング入門」「ホログラフィ入門 = INTRODUCTION TO HOLOGRAPHY : コンピュータを利用した3次元映像・3次元計測」が、漫画原作として「ブレインズ:コンピュータに賭けた男たち」や「永遠の一手 = Thought beyond time : 2030年、コンピューター将棋に挑む」があり、生粋の科学者である。「栄光なき天才たち」で伊藤氏が担当した巻は科学者を取り上げた話が多いが、このような知見のある伊藤氏の書かれたものはやはり説得力がある。
また、伊藤氏が手掛けた原作は、伊藤氏の公式サイト内の「漫画原作の部屋」に載っているので、漫画原作に興味のある人はぜひ読んでもらいたい。
一方、森田信吾氏はこの「栄光なき天才たち」が初連載の作品であった。森田氏は第一部の「栄光なき天才たち」の2、3、5、7、9、10、11、12、13巻の9冊分と、続編の「新・栄光なき天才たち」全3巻は原作者がなく森田氏1人で制作している。森田氏はその後の「栄光なき天才たち2009」(原案・新山藍朗氏)「栄光なき天才たち2010」「栄光なき天才たち2011」(監修・鈴木一義氏/原案・矢吹明紀氏)でも作画を担当している。
ノンフィクションの漫画で、様々な実在の人物を描くのは普通にフィクションの漫画を描くより難しい。本人に似せねばならず、かといって写実的に描いては漫画として成り立たない。あくまで本人の特徴を捕えて漫画的に表現しないといけないが、森田氏はその表現力が素晴らしい。特に7巻のマリリン・モンローは圧巻であると私は思う。スレンダーとは言い難い、すこし崩れた身体のラインでありながらも、マリリン・モンローの並外れた色気を放つ肉感的な魅力と不安定さを見事に表現していた。
「栄光なき天才たち」は、現在では当初のヤングジャンプ・コミックス版での入手は難しくなっているが、集英社文庫版(全4巻)、伊藤智義原作版(Kindle版全7巻)、栄光なき天才たち(森田信吾氏が全て手掛けたもののみ)(Kindle版全14巻)、大合本(全4巻)等、色々な形で読むことが出来る。気になる人物や分野が取り上げられているものがあれば、ぜひ手に取ってもらいたい。様々な天才たちの生き様は、きっと心に響くだろう。
そしていつかまた続編が出てくれることを期待している。







![【電子版】月刊コミックビーム 2026年3月号 [雑誌] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/510qLJC5+LL._SL160_.jpg)
![週刊少年サンデー 2026年12号(2026年2月18日発売号) [雑誌] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51k3d8R1gTL._SL160_.jpg)
![週刊少年マガジン 2026年12号[2026年2月18日発売] [雑誌] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/51igYObv58L._SL160_.jpg)

![コロコロコミック 2026年3月号(2026年2月14日発売) [雑誌] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/51JsckV8IAL._SL160_.jpg)

![週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年13号【デジタル版限定グラビア増量「ちーまき」】(2026年2月20日発売号) [雑誌] 製品画像:8位](https://m.media-amazon.com/images/I/51FTX6xiCgL._SL160_.jpg)
![週刊少年チャンピオン2026年12号 [雑誌] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51VWAYgC4SL._SL160_.jpg)
![ヤングマガジン 2026年12号 [2026年2月16日発売] [雑誌] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/516Te9JKoxL._SL160_.jpg)


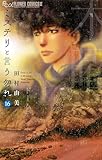



























![呪術廻戦 29 (ジャンプコミックス) [ 芥見 下々 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3773/9784088843773_1_33.jpg?_ex=128x128)
![呪術廻戦 30 (ジャンプコミックス) [ 芥見 下々 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3780/9784088843780_1_33.jpg?_ex=128x128)
![パラショッパーズ(4)【電子書籍】[ 福地翼 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2330/2000019602330.jpg?_ex=128x128)
![戦隊大失格(21)【電子書籍】[ 春場ねぎ ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5028/2000019645028.jpg?_ex=128x128)
![ガチアクタ(18)【電子書籍】[ 裏那圭 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5085/2000019645085.jpg?_ex=128x128)
![トニカクカワイイ(35) (少年サンデーコミックス) [ 畑 健二郎 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4851/9784098544851_1_17.jpg?_ex=128x128)
![MAO(27) (少年サンデーコミックス) [ 高橋 留美子 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4509/9784098544509_1_71.jpg?_ex=128x128)
![ブルーロック(37) (講談社コミックス) [ 金城 宗幸 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2045/9784065422045_1_2.jpg?_ex=128x128)
![葬送のフリーレン(15) (少年サンデーコミックス) [ 山田 鐘人 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3465/9784098543465_1_2.jpg?_ex=128x128)
![チェンソーマン 22【電子書籍】[ 藤本タツキ ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8211/2000018288211.jpg?_ex=128x128)
![聖者無双(16)【電子書籍】[ 秋風緋色 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5587/2000019605587.jpg?_ex=128x128)
![異世界で土地を買って農場を作ろう (11) (バーズコミックス) [ 岡沢六十四 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7308/9784344857308_1_3.jpg?_ex=128x128)
![アフタヌーン 2026年4月号 [2026年2月25日発売]【電子書籍】[ アフタヌーン編集部 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/7041/2000019767041.jpg?_ex=128x128)
![高校時代に傲慢だった女王様との同棲生活は意外と居心地が悪くない 3【電子書籍】[ ミソネタ・ドザえもん ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1295/2000019511295.jpg?_ex=128x128)
![寝取り魔法使いの冒険 7【電子書籍】[ 糸杉柾宏 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8972/2000019568972.jpg?_ex=128x128)
![ふたりソロキャンプ(23)【電子書籍】[ 出端祐大 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0974/2000019710974.jpg?_ex=128x128)
![昴と彗星(2) (ヤンマガKCスペシャル) [ しげの 秀一 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9143/9784065429143_1_2.jpg?_ex=128x128)
![[新品]ヘルモード ~やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する~ はじまりの召喚士 (1-13巻 最新刊) 全巻セット 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0034/m0308446151_01.jpg?_ex=128x128)
![[新品]トライガン TRIGUN セット (全16冊) 全巻セット 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0062/set-trigun_01.jpg?_ex=128x128)
![女友達は頼めば意外とヤらせてくれる(4)【電子限定特典付き】【電子書籍】[ ろくろ ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5228/2000019615228.jpg?_ex=128x128)
![恋するリップ・ティント 分冊版 26【電子書籍】[ 楠なな ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8932/2000019388932.jpg?_ex=128x128)
![[3月上旬より発送予定][新品]極と蕾 (1-5巻 最新刊) 全巻セット [入荷予約] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0061/m7890408482_01.jpg?_ex=128x128)
![青に落雷 10【電子書籍】[ 虹沢羽見 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1262/2000019511262.jpg?_ex=128x128)
![神さま学校の落ちこぼれ 13【電子書籍】[ 赤瓦もどむ ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/7159/2000019737159.jpg?_ex=128x128)
![隣のステラ(9)【電子書籍】[ 餡蜜 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6128/2000019296128.jpg?_ex=128x128)
![暁のヨナ 47 (花とゆめコミックス) [ 草凪 みずほ ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5690/9784592225690_1_27.jpg?_ex=128x128)
![今日きみの手をとってあの空の下 4【電子書籍】[ 宮川匡代 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8912/2000019758912.jpg?_ex=128x128)
![デザート 2026年4月号[2026年2月24日発売]【電子書籍】[ 旗谷澄生 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6879/2000019766879.jpg?_ex=128x128)
![花野井くんと恋の病(18)【電子書籍】[ 森野萌 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9497/2000018809497.jpg?_ex=128x128)
![花野井くんと恋の病(17)【電子書籍】[ 森野萌 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8349/2000017588349.jpg?_ex=128x128)


![【楽天ブックス限定デジタル特典】QuizKnock10周年スペシャルブック 十字路(ロケ撮影メイキング映像 ダウンロード) [ QuizKnock ] 製品画像:11位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9436/9784048979436_1_9.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】超ときめき宣伝部 吉川ひより1st写真集(フォトカードA(トレカサイズ)1枚) [ 吉川 ひより ] 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4415/2100014804415_1_2.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定特典】佐野なぎさ1st写真集(限定絵柄生写真) [ 佐野なぎさ ] 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8114/2100014828114_1_2.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定特典】乃木坂46川崎桜 1st写真集『エチュード』 2冊セット(通常カバー+限定カバー)(限定絵柄ポストカード1枚) [ 川崎桜 ] 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1023/2100014821023_1_3.jpg?_ex=128x128)
![【特典】夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日 メイキングDVD付限定表紙版(限定カバー【Amazon・楽天ブックス限定】) [ 夏吉ゆうこ ] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8098/9784065398098_1_3.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定特典】櫻坂46写真集 櫻撮VOL.01(限定カバー) [ 櫻坂46 ] 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2143/9784065432143_1_4.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定特典】乃木坂46川崎桜 1st写真集『エチュード』(限定カバー) [ 川崎桜 ] 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1009/2100014821009_1_3.jpg?_ex=128x128)